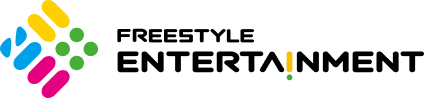プレゼンテーションを成功させるためには、聴き手の心に響く論理的な構成が重要です。「伝えたいことは多いのに、話がまとまらない」「独りよがりな資料になっていないか不安」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、社内会議から外部への提案まで、様々な場面で活用できる具体的な構成の作り方を詳しくご紹介します。あわせて、内容の説得力を格段に高める資料作成のコツもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
【パワポ】プレゼン資料の構成が重要な理由

プレゼンテーションの成否は、スライドのデザインや話し方の技術だけでなく、その土台となる「構成」によって大きく左右されます。事前に構成を固めておくことが重要な理由は、以下の通りです。
- 聴き手の理解を促進して納得感を高めるため
- 資料作成を効率化して工数を短縮するため
- 話し手自身の自信につながるため
聴き手の理解を促進して納得感を高めるため
プレゼンテーションの目的は、聴き手に内容を正しく理解してもらい、行動を促すことです。そのためには、話が論理的に整理されている構成が不可欠です。
人間は、情報が体系的に順序立てて提示されると、スムーズに頭に入れることができます。明確な構成は、聴き手が話の全体像を把握し、現在地を見失うことなく、安心して話に集中できる道しるべの役割を果たします。
資料作成を効率化して工数を短縮するため
いきなりスライド作成に着手すると、途中で話の順序を入れ替えたり、不要なスライドを作ってしまったりと、多くの手戻りが発生しがちです。
最初にプレゼン全体の骨子となる構成を固めることは、家を建てる際の設計図を作ることと同じです。構成を事前に固めることで、各スライドで何を伝えるべきかが明確になるため、作業の迷いがなくなり、一貫性のある内容を効率的に作成できます。
構成という土台があることで、情報の過不足や重複を事前に防ぎ、資料作成全体の工数を大幅に短縮することが可能です。
話し手自身の自信につながるため
しっかりと練り上げられた構成は、話し手にとって最大の心の支えとなります。話すべき内容とその順序が明確になっているため、「次に何を話せばよいか」という不安が解消され、堂々とした態度でプレゼンに臨むことができます。
たとえ緊張してしまっても、話の道筋さえしっかりと頭に入れておけば、落ち着いて進行することが可能です。また、構成を考える過程で内容への理解が深まるため、予期せぬ質問にも的確に答えやすくなります。
この「準備ができている」という感覚が、自信のあるプレゼンテーションにつながり、聴き手への説得力を一層高めます。
プレゼン資料の構成を考えるフレームワーク

パワーポイントでプレゼン資料の構成を考える際、フレームワークを活用することをおすすめします。
フレームワークとは、話の流れを論理的に整理し、聴き手の理解と納得感を引き出すための「型」です。フレームワークを目的に合わせて使い分けることで、説得力のあるプレゼンテーションを効率的に作成できます。
今回ご紹介するフレームワークは、以下の通りです。
- SDS法
- PREP法
- FABE法
- DESC法
- TAPS法
SDS法
SDS法は、Summary(概要)→Details(詳細)→Summary(まとめ)の流れで、物事をわかりやすく伝えるための基本的なフレームワークです。このフレームワークは、プレゼンテーションの王道で、汎用性が高くさまざまな場面で利用されます。
- Summary:全体の概要
最初にプレゼン全体で伝えたいことの要点を伝える - Details:詳細な説明
具体的なデータや事例を交えながら詳しく説明する - Summary:最後のまとめ
最後に、話した内容全体をもう一度要約して締めくくる
SDS法は、シンプルでわかりやすく、聴き手が話の全体像を把握しやすい構成になっています。短時間でわかりやすい説明が求められるような場面に適しているフレームワークです。
PREP法
PREP法は、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)の順で情報を整理するフレームワークです。ビジネスシーンでの報告や提案など、説得力とスピードが求められる場面に適しています。
- Point:結論
最も伝えたい結論や主張を最初に述べる - Reason:理由
その結論に至った理由や根拠を説明する - Example:具体例
理由を裏付けるためのデータやエピソードを提示する - Point:結論の再提示
最後にもう一度結論を述べて主張を明確に印象付ける
最初に結論から伝えるため、メッセージが明確に伝わりやすく、論理的かつ説得力のあるプレゼンテーションを実現することが可能です。
FABE法
FABE法は、Feature(特徴)→Advantage(優位性)→Benefit(便益)→Evidence(証拠)の流れで、主に商品やサービスの紹介や営業で用いられるフレームワークです。このフレームワークで商品やサービスのプレゼンテーションを行うことで、提案内容を具体的かつ魅力的に伝えることができるようになります。
- Feature:特徴
商品やサービスが持つ客観的な特徴や仕様を説明する - Advantage:優位性
その特徴が競合他社のものと比べてどう優れているのかを説明する - Benefit:便益
優位性が顧客にどのようなメリットを与えるのかを伝える - Evidence:証拠
その便益が本物であることを示す客観的な証拠を提示する
商品のスペックをただ説明するだけでなく、顧客にとってのメリットや価値(ベネフィット)にまで落とし込んで伝えられるため、購買意欲を高めることができます。
DESC法
DESC法は、Describe(描写)→Explain(説明)→Specify(提案)→Choose(選択)の流れで、相手との合意形成を目指すフレームワークです。このフレームワークは、単に情報を伝えるだけでなく、具体的な行動を促すことが大きな目的です。
- Describe:描写
解決すべき課題や状況を客観的な事実として伝える - Explain:説明
描写した事実に対する自身の意見や見解を説明する - Specify:提案
具体的な解決策や相手にしてほしい行動を明確に伝える - Choose:選択
提案を受け入れた場合とそうでない場合の結果を示して選択を促す
DESC法は、聴き手に何かを承認してもらいたい提案の場面や、問題を解決するために協力をお願いする場面で強力な効果を発揮します。
TAPS法
TAPS法は、To be(あるべき姿)→As is(現状)→Problem(課題)→Solution(解決策)の流れで、ストーリー仕立てで課題解決までの道筋を示すフレームワークです。聴き手に現状と理想とのギャップを明確に伝えることで、提案する必要性を深く理解してもらいやすいことが大きな特徴です。
- To be:あるべき姿
聴き手が共感するような理想の状態や目指すべき姿を提示する - As is:現状
現在の状況や問題点を客観的な事実に基づいて説明する - Problem:課題
あるべき姿を目指すための課題を提示する - Solution:解決策
提示した課題を解決するための具体的な解決策を提案する
このTAPS法は、現状を変革するための新しい提案や、顧客がまだ気付いていない課題に対して提案する場面に適しています。
パワポでわかりやすい資料を作るポイント

資料全体の構成をわかりやすく作るためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 目的と提案の軸を明確に定める
- 提案する相手の立場を第一に考える
- 各章のボリュームのバランスを考慮する
目的と提案の軸を明確に定める
資料作成に着手する前に、「この資料を通じて相手にどうなってほしいのか」という最終目的と、そのために「最も伝えたい核心は何か」という提案の軸を明確に定めることが重要です。この軸が、全体の構成を貫く背骨となります。
最初にこの背骨を固めることで、盛り込むべき情報や話の順序を判断する際の迷いがなくなり、論点がブレません。結果として、メッセージが散漫にならず、一貫性のある力強い構成を組み立てることができます。
提案する相手の立場を第一に考える
構成を考える際は、常に「相手が知りたい情報は何だろうか」「どのような順番で聞けば最も理解しやすいか」という、相手目線を貫くことが重要です。例えば、多忙な決裁者向けであれば結論から先に、現場の担当者向けであれば背景や手順から丁寧に、といった配慮が求められます。
相手の役職、知識レベル、関心事を考慮して構成を最適化することで、独りよがりな説明を避け、相手の心に響き、納得感を引き出す説得力の高い資料になります。
各章のボリュームのバランスを考慮する
プレゼンテーション全体に心地よいリズムと流れを生むために、各章のスライド枚数や時間の配分を意識することが大切です。一般的に、聴き手の関心を掴む「序論」と、内容をまとめる「結論」は全体の10%ずつ、最も重要な「本論」に80%程度のボリュームを割くのが黄金比とされます。
本論の中でも、特に主張を支える重要な根拠や具体例の部分は手厚く説明する、重要度に応じてメッセージに強弱をつけるなどの工夫が大切です。そうすることで、聴き手を飽きさせず、効果的にメッセージを伝えることができます。
伝わる資料作りはプロに依頼するのもおすすめ
パワーポイントでわかりやすい資料を作るためには、専門的な知識や技術が求められ、時間もかかります。もしリソースが不足していたり、より高い成果が求められる重要な場面であったりする場合には、プロの資料作成代行サービスに依頼するのも有効な選択肢です。
専門家ならではの構成力とデザイン力で、伝えたい内容が的確に伝わる、説得力の高い資料を効率的に手に入れることが可能です。
株式会社フリースタイルエンターテイメントでは、提案資料や企画書など、あらゆるプレゼンテーション資料の作成を代行するサービスを提供しております。パワーポイントでの資料作成に精通したスタッフが、目的やシーンに合わせて最適な資料作成を代行し、ビジネスの成功に貢献します。
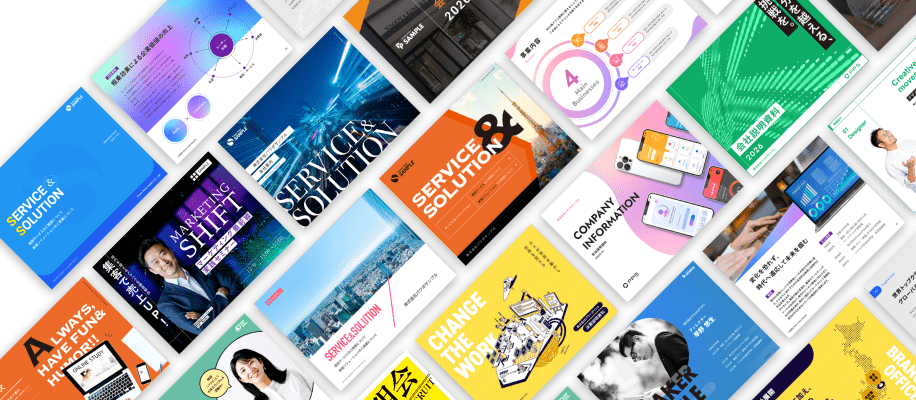
企画・構成まで
プロにお任せ
パワーポイント制作
構成を考える際のよくある質問

プレゼン資料の構成を作る際によく挙げられる質問と回答を、以下にまとめます。
Q.何から手をつければ良いですか?
まずはパワーポイントを開かずに「設計」から始めるのが成功の秘訣です。
多くの方がいきなりスライドを作り始めてしまいがちですが、それが手戻りや話の脱線の原因になります。まずは紙やテキストエディタで、以下の3点を書き出してみましょう。
- 目的とゴール:聴き手にどうなってほしいのか
- 聴き手の分析:相手は誰で、何を求めているのか
- 話の骨子:伝えたい核心メッセージは何か
この「設計図」が完成してから初めてパワーポイントを開くことで、作業がスムーズに進み、一貫性のあるわかりやすい資料を効率的に作成できます。
Q.どのフレームワークを選べば良いですか?
最適なフレームワークは、プレゼンの目的や状況によって大きく異なります。
例えば、結論から先に伝えて素早く説得したい場合はPREP法が、まず話の全体像を示して分かりやすく説明したい場合はSDS法が適しています。TAPS法はストーリー仕立てで、聞き手の共感を呼びたい提案や商談の際に最適です。
上記のように、各フレームワークの特徴を理解し、自身の置かれた状況やプレゼンの目的に合わせて柔軟に選ぶことが重要です。
Q.資料全体でスライドの最適な枚数は何枚くらいですか?
スライドの枚数に絶対的な正解はありませんが、一般的に「プレゼンの持ち時間」と「1スライドに割く時間」を基準に考えます。
例えば、20分のプレゼンで、1スライドを平均1分で説明する場合、20枚が一つの目安です。しかし、質疑応答の時間や、1枚のスライドをじっくり説明する場面を考慮すると、15枚〜20枚程度に収めると、余裕を持って話しやすくなります。
枚数を増やすことよりも、1枚1枚のスライドでメッセージが明確に伝わるかを重視することが大切です。
プレゼンで勝てる資料は構成が鍵を握っている
本記事では、伝わるプレゼンのための構成の重要性や具体的なフレームワークを解説しました。優れたデザインやトークスキルも、土台となる論理的な構成があってこそ活きてきます。
今回ご紹介したフレームワークやポイントを参考に、聴き手の心を動かし、目的を達成する「勝てる」プレゼン資料を作成してみてください。
「資料作りにあまり自信がない」「資料を作り込みたいが時間がない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ株式会社フリースタイルエンターテイメントまでご相談ください。資料作成のプロが、論理的でわかりやすくデザインされたプレゼン資料を提供します。
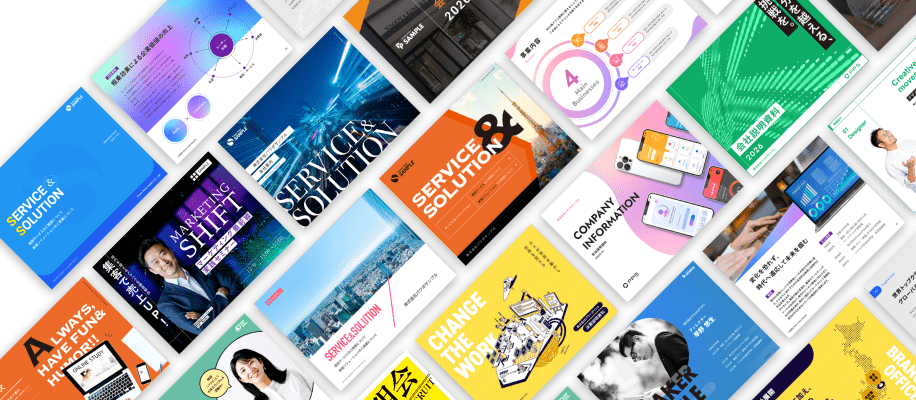
伝わるパワーポイント
制作はお任せください